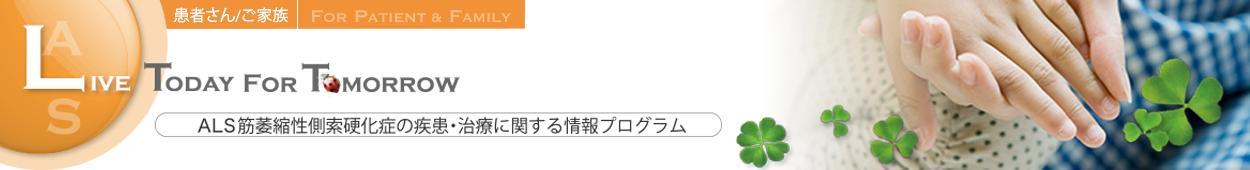

エピソード15
人工呼吸器を付けたALSの患者さんを在宅で看取るということ
人工呼吸器を付けて自宅あるいは病院でALSと闘っている患者さんは数多く存在し、その生きる努力、周囲の介護努力を見て、私たち医療関係者が逆に励まされるケースが多々あります。
しかし、残念ながらこうしたALSの患者さんにも、「死」の瞬間がいつかは訪れます。これは、健康な人にも常に「死」が訪れる可能性があるのと同じです。
私が訪問看護チームの主任を担当していた数年前、人工呼吸器を付けて在宅療養していた患者さんが、自宅で息を引き取りました。
私がこの「カルテの余白」で述べたいのは、その際の患者さん自身のエピソードではなく、在宅でALSの患者さんを看取る医療側の問題と訪問医療体制の問題です。
発病から人工呼吸器装着までの経過
この患者さん(60歳の男性)の発病は、1995年9月でした。
右手の前腕がピクピクするようになり、1カ月後には両腕が上がらなくなりました。10月後半には、M市立病院で「ALSの疑いあり」と診断されました。
同年11月には、文字を書くことや箸の使用が困難になり、階段の昇降もできなくなりました。発症して早くも2カ月で急速に手足の運動障害が進行したのです。
12月に某大学附属病院脳神経センターを受診し、その年末から新年にかけて入院した際に、上気道の感染により危険な状態に陥りました。
1996年2月1日、気管切開、人工呼吸器を装着しました。発病してわずか4カ月で、事態がどんどん進み、症状は急激に悪化しました。
その後の闘病生活
1996年3月中旬(発症後6カ月目)には球麻痺症状が進行して胃瘻造設術を施行しました。
さらに同月末には院内感染MRSAによる肺炎を併発します。肺炎により、胸水がたまるようになって、なかなか回復しませんでした。
そのような状況のなかで、どうしても在宅療養をしたいという患者さんのたっての願いで、自宅に帰ることになり、同年6月に自宅から遠くない私たちの病院に紹介されてきました。
人工呼吸器の装着
人工呼吸器を装着するかどうかについて、患者さんご本人は消極的だったそうです。しかし、ご家族の非常に強い希望があり、呼吸器を装着することになったと記録されています。
在宅で介護されるご家族の数は十分で、奥様、長男夫婦、次男夫婦、患者さんの妹2人が、それぞれ分担して介護にあたることになりました。 病院の看護師は、長男の奥さんにカニューレ交換と胃瘻チューブ交換を指導し、それ以外のご家族には吸引、体位交換、排泄の介助、全身状態の観察、経管栄養の管理、薬の投与、浣腸、座薬の挿入、清拭、車イスへの移乗、シーツ交換などを徹底して教えました。ご家族は非常に意欲的に短期間で在宅療養の体制を整えられました。
人工呼吸器を装着しての在宅療養体制は万全で、ほとんど問題はありませんでした。ただ、胸水だけは貯留していてなかなか引かず、抗生物質を投与しても、穿刺(針を刺して)して胸水を引き抜いても、あまり効果はありませんでした。
このような状態だったので、体位交換をするとき、呼吸が苦しくなり、痛みを強く訴える状態が続きました。
在宅療養の訪問看護と介護体制
こうしてスタートした在宅療養でしたが、患者さんが胸痛を強く訴えるので、当院では、肺炎の再発、敗血症の再発に備えて、緊急の受入れ体制を整えていました。病状が悪化した際は、日中は神経内科の外来へ、夜間は当病院の病棟4階に直接連絡して入院できるように準備していました。
定期的に毎月1回、神経内科医と当院の訪問看護師、ソーシャルワーカー、人工呼吸器を管理するME(臨床工学技術士)、近くの開業医の先生、近くの訪問看護師らが患者さんを定期往診し、諸々をチェックしました。医師を除く定期訪問は2週間に1回でした。
日常のチーム医療体制は、近くの開業医の先生と訪問看護師、ご家族とヘルパーさんで構成され、何事もなく良好な状態ではありましたが、ご本人の胸痛による強い苦痛は少しも好転しませんでした。
2年半後再び状態が悪化したときに・・・
人工呼吸器を装着して3年弱、在宅療養を始めて2年半後の1998年末、徐々に意識が落ちてきました。当初、電解質異常が原因ではないかと考えて治療にあたりましたが、やはり効果がなく、障害が強くなっていきました。
以前からこの患者さんご自身もご家族も在宅死を望んでおられたので、病院に入院せずに、状態を見守ることになりました。
このようなとき、人工呼吸器を付けて在宅療養する患者さんとご家族にとって、非常に不安になる問題があります。現在の日本の医療体制では、土曜日、日曜日などに緊急の事態が起こったとき、近くの主治医が休診日で不在、訪問看護ステーションも閉まっている、というケースが少なくないのです。当病院では神経内科の医師による当直医はいますが、外へ往診に行くことはできません。
では、もしも休日に人工呼吸器を付けた患者さんに異変が起こった場合、ご家族はどうすればいいのか――。
在宅死を望むのはだれにとっても究極の願い
他の疾患の、例えばがんの患者さんにとっても、在宅死は常に強い要望として挙げられています。私自身、在宅死は人生の最期を迎えるのにより理想的な終焉(しゅうえん)であると考えています。しかし、人工呼吸器を付けた患者さんが在宅死を望んだ場合、今の日本の医療体制では、残念ながら十分対応できるとはいえないところに難しい問題があります。
医師の24時間訪問体制をどうつくるのか
在宅医療体制を整備するということは、どのような事態が起ころうとも、医師が原則的にきちんと対応できる体制をつくることにあります。ALSの患者さんの定期的な往診は、患者さんが安定した状態だからこそ順調に行えますが、急激に悪化したり、緊急事態になった場合、最後まできちんとシステムをつくって対応することができるかどうかが、人工呼吸器を付けたALSの患者さんの在宅死を可能にするかどうかの重要なファクターになります。それは、人工呼吸器を付けた患者さんの死亡を医師はいつ、どのように確認するのかという点で、問題をより複雑にしているからです。
人工呼吸器を付けている患者さんの死亡確認は、専門医や主治医が重態の患者さんのそばに付いていなければ不可能で、高度な判断が必要とされます。
休日の緊急事態に、ALS専門医または近くの主治医が常に往診できる状態になっているのでしょうか。
現在の体制では、ほとんど不可能に近いといわざるを得ません。上記の患者さんの場合は、私と訪問看護師の2人が休日待機しましたが、こうした事態を個々の医療関係者の自発的意志や努力に頼って解決している限りは、人工呼吸器をつけたALSの患者さんを在宅で看取ることを標準の医療とすることは、困難ではないかと思われます。
約6,000人近い患者さんが、24時間対応してくれる医師を必要としている
在宅医療についての推計では、現在日本国内に、約6,000人近い患者さんが24時間対応してくれる信頼できる医師を必要としているそうです。
したがって、在宅死を含めて、在宅療養を責任もって支援する医療体制を整備するには、専門医をはじめ4~5人の必要な医療スタッフの揃ったクリニックが、全国で1,000カ所程度必要だという試算があります。
私はこうした往診システムが一日も早く整備され、人工呼吸器を付けた患者さんが安心して在宅療養でき、自宅で何の不安もなく人生の最期をまっとうできる日が来ることを願わずにはいられません。
MAT-JP-2108393-2.0-12/23






%20(1).png)

