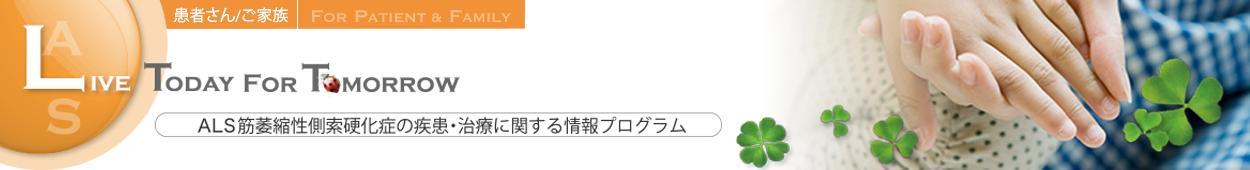

エピソード5
在宅で見事に人生の幕を閉じたGさん
私は14年間北里大学東病院で約111名のALSの患者さんの診療にあたってきましたが、そのなかで非常に印象的な患者さんについてご紹介します。

人工呼吸器装着か否かの選択
Gさんは、神奈川県在住のクリーニング店の奥様で、43歳でALSに罹患するまでほとんど病気らしい病気を知らず、ご主人と一緒に家業ひとすじに毎日忙しく立ち働いていました。お子さんは、当時大学生の娘さん、息子さんの2人でした。
突然しゃべりにくくなり、疲れを覚えるようになったのは1993年、43歳の半ばを過ぎたころでした。ご主人とあちこちの病院を廻った後、北里大学東病院を受診され、筋電図などの諸検査の結果ALSと診断しましたが、そのときすでに軽い球麻痺症状や、上肢の疲れ、筋肉の萎縮が起こっていました。
やがて、下肢が動かなくなり、人工呼吸器をつけて在宅療養するかどうかをそろそろ考えなければならない時期に来ていると判断し、Gさんの地元保健所の保健婦さん、担当の病院ナース、ボランティアの方たちを集めて、会議をもちました(「在宅人工呼吸療法実施手順の図」はこちらをクリック)。
この第1回目の会議は、患者さんとご家族を含まずに、在宅人工呼吸療法が可能かどうかを検討する会議です。当時、訪問看護ステーションはなく、病院ナースによる訪問看護や、ボランティアの人たちの協力を得られる見通しがあり、保健婦さんや担当のナースたちも、非常に熱心に在宅介護チームを作って実現しようという意志の確認がありました。
その後、患者さんとご主人を呼んで、「徐々に呼吸が苦しくなるので、在宅で人工呼吸療法をするかどうか本格的に考えましょう」という趣旨のインフォームドコンセントを行ったのです。
そのとき、Gさんは「家族で話し合うので、少し時間がほしい」と言われました。
その約10日後、今度は患者さんやご家族の方も含めて、第2回目の検討会議を開きました。まだご本人の意志が固まっていない段階なので、人工呼吸器をつける、つけないを別にして、もう一度可能性について全員で検討するために開かれた会議でした。
その席でGさんご本人の口から出たのは、「人工呼吸器はつけない」という言葉でした。
条件や環境は十分そろっているし、ご主人、娘さん、息子さんはつけて生きてほしいと強く願っているにもかかわらず、ご本人は頑として「つけない」とおっしゃるのです。
その理由を聞くと、「自分が何の目的で人工呼吸器をつけるのかわからないのです。私はQOLを上げるようなことは何もできません。これまで家業ひとすじに生きてきて、子供もここまで成長したし、この先仕事も家事もできないのなら、人工的な手段を使ってまで生きたくはありません」と、強い意志表示があり、人工呼吸器をつけないことを選択されました。
人工的な手段をとらずに在宅死を迎えたGさん
その後、近くの開業医の先生や保健婦さん、当病院ナース、ボランティアなどの助けを借りて、半年間ほど在宅療養を続けていました。私は、その間Gさんの様子についてナースなどから報告を受けていたので状況はすべて把握していましたが、本人の意志を尊重してあえて病院へ来るようにという指示は出しませんでした。
やがて、ほとんどしゃべることも食べることもできなくなり、呼吸麻痺が強くなってきたので、家族は病院への入院をすすめました。しかし、人工的な手段を使って生きるのはいやだというご本人の意志は固く、そのまま経管栄養も使わずに在宅療養を続けました。
自分の人生の幕を自分で下ろすかのように、亡くなる前日、ボランティアの方に、お風呂に入りたいと望んで、とても気持ちよさそうにお風呂に入れてもらい、下着もシーツもすべて取り替え、部屋の中もきれいに片付けてもらって家族全員を枕もとに呼ばれたそうです。そこには、おそらく手が動くときにすでに書いたと想像される家族への手紙が置いてあり、「まわりの人たちすべてにお世話になり、ありがとうございました」とあふれるような感謝の言葉がしたためられていました。
亡くなる当日は、ほとんど意識がなく、痛みもないまま眠るように人生の幕を閉じられたと看取られたご家族から聞いています。ALSを発症してわずか2年の闘病生活、享年45歳でした。
私は大学病院勤務を始めて30年になりますが、難病患者のなかでもこのように見事な最期を迎えた方はそれほど多くはありません。たとえ、治療法のない難病にかかっても、自分の人生をいかに生きるかという明確な意志をもって、人工的な手段にたよらず、自分の家でまわりの人に感謝しながら人生の幕を閉じる、というGさんの生き方は、Gさんなりに見事に「病気を克服して人生をまっとうされた」といえるのではないでしょうか。
MAT-JP-2108393-2.0-12/23






%20(1).png)

