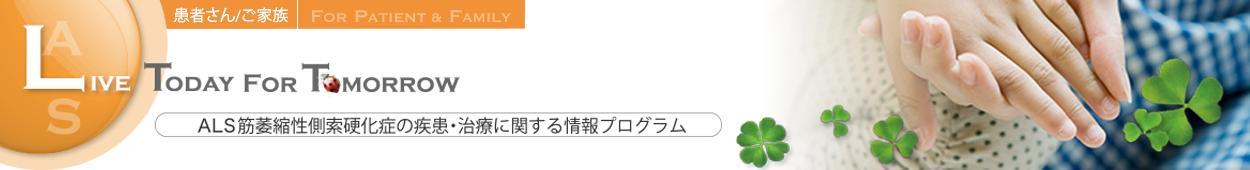

エピソード6
思いを短歌に託したSさんと献身的に看病されたご主人
私が北里大学東病院に赴任して間がないころ、別の病院から救急車で運ばれてきたALSの患者さんがいました。それがSさんで、高校の校長を定年退職された方の奥様でした。
最初に診察したとき、Sさんはすでに上肢、下肢とも筋力が低下して、球麻痺もかなり進んでいました。横浜市に住まいがあったので、私が時々往診し、呼吸が苦しくなると国道16号線を利用して病院へ移送し、時には救急車で、ということを数回繰り返すという状態でした。しかし、人工呼吸器はつけたくないというご本人の強い要望があったので、自然の状態にまかせていました。

SさんはALSに罹患する前から趣味で短歌を詠んでおり、60歳で発症した後も筆を折ることなく続けておられたそうです。
ご主人はすでに高校の校長を退職しておられたので、Sさんが発病されてからは献身的に看病されていました。
Sさんが亡くなった後、ご主人から私に一枚の短冊が送られてきました。そこには、Sさんが闘病中に詠まれた短歌の一首が書いてありました。 その内容は「横で夫がいびきをかいて寝ている。私は体が痛くて眠れないけれど、看病に疲れて寝ている夫を起こさずに我慢しよう」というつらい気持ちを詠んだ歌でした。
ご主人は、Sさんの生前、短歌を詠んでいることは知っていたけれども、看病に手一杯で、どんな歌を詠んでいるのか、まったく気にも留めなかったといいます。
亡くなった後、Sさんが残した歌を見て、こんなにつらい思いをしていたのかと涙が止まらなかったそうです。
患者さんの手足の麻痺が進んで、会話の障害も起こると、体位変換一つをとっても非常にむずかしくなります。ほんの数ミリ位置や角度が違っただけで、患者さんは身体の一部に痛みを感じたり、眠れなかったりします。Sさんは、介護で疲れて眠っている夫を体位変換のために起こすのは、しのびなかったのかもしれません。
介護される患者さんは、介護者への感謝と遠慮と要求の入り混じった複雑な気持ちで毎日をすごしていると思われます。Sさんは、67歳で亡くなるまで症状の進行が比較的緩やかだったので、趣味の短歌を楽しむかたわら、長い闘病生活期間中の人には言えない複雑な気持ちを、短歌に託して表現し、自分自身を慰めておられたのでしょう。
Sさんは私が北里大学東病院に来てまだ日も浅い頃の患者さんで、何度も自宅へ往診させていただきましたが、身体の動かないSさんを献身的に看病されたご主人と、短歌で自己表現をして人生をまっとうされたSさんのご夫婦の生き方を見せていただいたように思います。
MAT-JP-2108393-2.0-12/23






%20(1).png)

